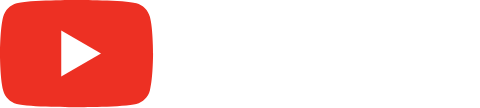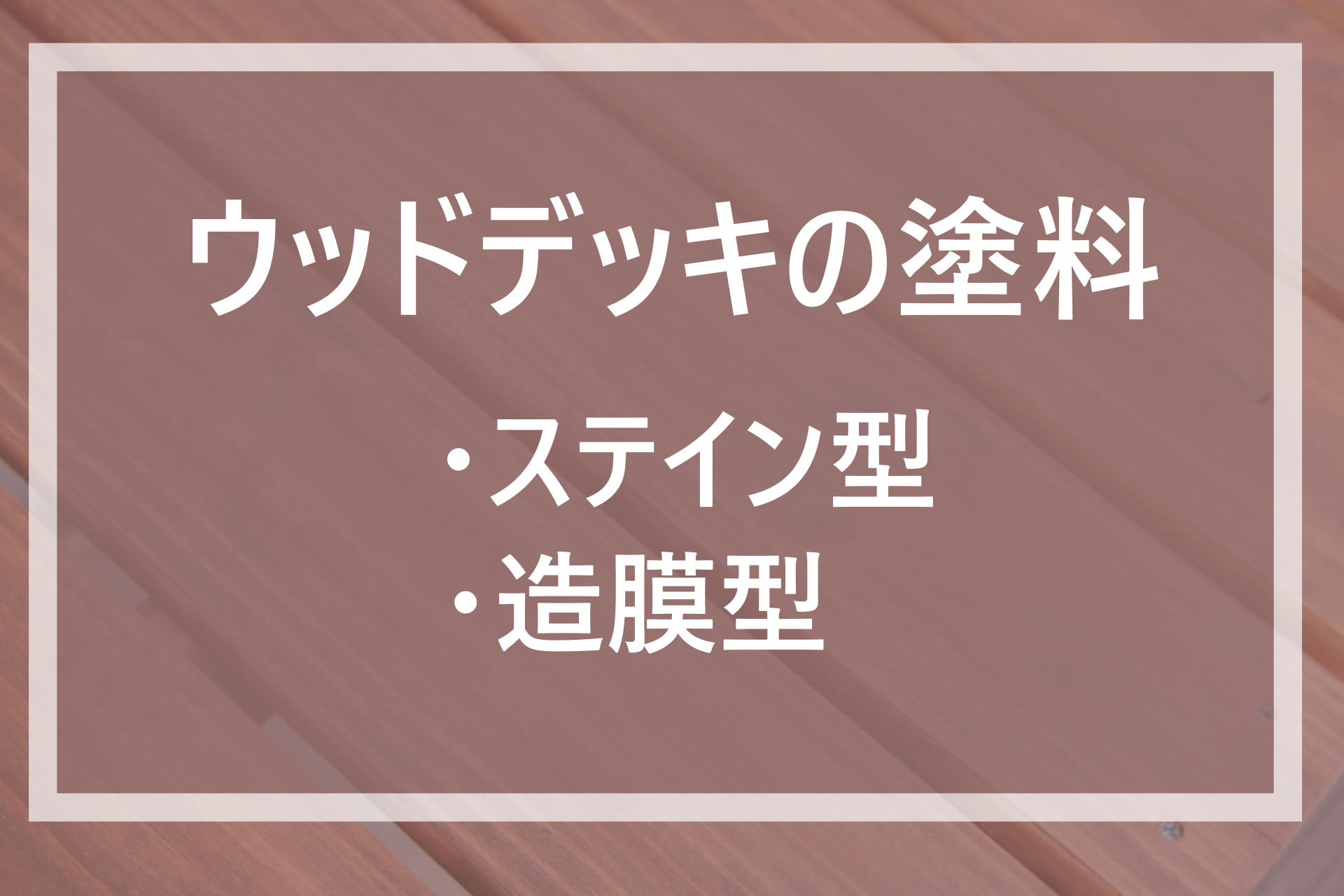ウッドデッキの塗装におすすめの塗料・手順を詳しく解説
ウッドデッキは木材だけでなく、塗装をすることで見た目が美しくなるだけでなく耐久性も高まります。
ウッドデッキの塗装は設置時以外にも数年おきの塗りなおしが必要なので、きちんとした知識を付けたいという方も少なくないのでは?
この記事では、
ウッドデッキにおすすめの塗料
塗装の手順
塗りなおす頻度
について詳しく解説いたします。
負担の少ないウッドデッキについてもご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1.天然木でウッドデッキを作る場合は塗料が必須
ウッドデッキ用の塗料は天然木、特にソフトウッドを使用する時には必要不可欠です。
ウッドデッキで使う塗料は見た目以外にも、防腐・防虫効果など耐久性を左右するためです。
また、適切なスパンで塗りなおしをすることでささくれや割れを防いでくれるため、使用感にも影響します。
虫に強く耐久性の高いハードウッドを使う場合は、素材の風合いを活かすために敢えて塗料を塗らない人もいますが、長く使う内に色あせたり木肌がささくれたりするので、メンテナンスとして塗料を使うケースも一般的です。
2.ウッドデッキ用の塗料はステインと造膜型
ウッドデッキ用の塗料は大きく分けて、
ステイン(浸透)タイプ
造膜(エナメル)タイプ
の2パターンがあります。
2-1.木目を生かすステイン
ステインタイプの塗料は、サラっとしていて木材に染みこみます。
木目が透けるので、色味を調節しながら自然に仕上げたい人におすすめです。
防腐・防虫剤が入ったステインタイプの塗料を使うと、木材の耐久性もアップします。
木材に染みこむという特性上塗りなおしがしやすいというメリットがありますが、雨や湿気などの水分を防ぐわけではないため、造膜タイプと比べて再塗装のスパンが短くなりがちです。
2-2.造膜塗料は古くなった木材の保護にも
造膜タイプは、木材に染みこまずにペンキのように表面に膜を作る塗料です。
はっきりとした色味にしたい、古くなった木材のアラを隠したい場合に向いています。
塗料による膜により、ステインタイプと比べて湿気や外部要因からの保護力は高め。
ただし、塗装面がひび割れてしまうとそこから水分が入ってしまう、塗りなおし時の処理が面倒といったデメリットがあるようです。
3.ウッドデッキ塗装の方法を手順ごとに解説
ウッドデッキ塗装の方法と注意点、必要なアイテムなどを、手順ごとに詳しく解説いたします。
3-1.掃除・木材の下処理
ウッドデッキ設置時に塗装する場合は木材の下処理を、再塗装する際はデッキの掃除を行いましょう。
この時に必要なのは、
軍手
サンドペーパー(またはやすり)
ブルーシート
布やブラシ
の3点です。
木材の表面にやすりをかけることで、塗料の浸透が良くなる効果が期待できます。
再塗装する場合は、まずウッドデッキと周辺をきれいにしてから下処理をしましょう。
材質ごとのウッドデッキ掃除方法と必要なグッズについては、こちらで詳しくご紹介しております。
内部リンク:https://nuan.jp/column/1202/
最初の塗装の際は軽くやすり掛けする程度で大丈夫です。
木くずが出るので、ブルーシートの上で作業すると片付けやすくなります。
塗りなおしする際、特に造膜タイプの塗料が残っている場合はしっかりとやすりがけをすることが大切です。
全て手作業だと労力も増えるので、電動サンダーなどがおすすめです。
サンドペーパーを使う場合は最初に粗いものを使って、仕上げに細かい目のやすりをかけると滑らかに仕上がります。
この時塗料だけでなく、木材自体にデコボコがないか、割れやささくれがないか確認してください。
やすりがけが終わったら、表面を刷毛やブラシなどで大まかに払ってから、布や雑巾で表面をきれいにしましょう。
3-2.シートとテープで養生
塗料を付けたくない部分にブルーシートや養生テープを使って、養生しましょう。
養生するのは窓、デッキ下、住宅の外壁、堀など。
デッキ近くに植物などがある場合は念のため塗装が終わるまでビニール製のシートなどをかけておいてもいいかもしれません。
3-3.下塗り
下準備が終わったらいよいよ塗料を塗っていきます。
塗料の缶を開ける前によく振ってムラをなくしましょう。
デッキの隙間や溝
↓
表面
↓
裏面
という順番で塗ると、塗り忘れやムラが出にくく綺麗に仕上がります。
狭い部分は刷毛やブラシで、広い面はローラーを使って塗ると効率良く作業できます。
木材の傷等が目立つ場合は、木工用プライマーを使っても良いでしょう。
3-4.重ね塗り
きれいに塗りを完成させるコツは、「少量ずつ何回かに分けて塗る」ことです。
一度にたっぷり塗料を乗せてしまうと、ムラになる上に乾きにくくなってしまいます。
塗料を塗ったらしっかりと乾かして、また塗って乾かす・・・という作業を3回ほど繰り返します。
乾燥時間は天候や塗料のタイプによって異なりますので、塗料のパッケージなどをよくご確認ください。
3-5.乾燥・片付け
指定された時間にしっかりと乾かしたら、養生などを片づけて作業は完了です。
清掃から乾燥までそれぞれの工程を丁寧にすると、3〜5日はかかるので晴れが続くタイミングで塗装を行いましょう。
4.ウッドデッキ塗装で失敗しないための注意点
ウッドデッキの塗装は、美観の維持や耐久性の向上に欠かせません。
しかし、適切な手順や注意点を守らないと仕上がりにムラが出たり、塗膜の剥がれが早まったりすることがあります。
ここでは、塗装で失敗しないためのポイントを解説します。
4-1.塗装前の下地処理を徹底する
塗装の前にウッドデッキの表面をしっかりと清掃し、汚れ・カビ・古い塗膜を取り除くことが重要です。
高圧洗浄機やデッキブラシを使用して、表面の汚れを丁寧に落としましょう。
とくに古い塗膜が剥がれかけている場合は、サンドペーパーで滑らかに整えることで新しい塗料の密着性が上がります。
4-2.適切な塗料と道具の選択
ウッドデッキには、木材専用の塗料を使用することが推奨されています。
浸透型の塗料は木材内部に浸透し、木目を活かした仕上がりに。
一方、造膜型の塗料は表面に膜を作り耐久性を高めるので目的や好みに応じて選択してください。
また、塗装にはハケやローラーを使用しますが、細かな部分や隙間にはベンダーと呼ばれる専用の道具を使うとムラなく塗装できます。
4-3.塗装環境とタイミングの確認
塗装は、気温15~25℃で湿度が低い晴天の日に行うのが理想的です。
雨天や高湿度の日は、塗料の乾燥が遅れ仕上がりに影響を及ぼす可能性があります。
また、直射日光が強い時間帯は避け、朝や夕方の涼しい時間帯に作業を行うと塗料の乾燥が均一になります。
4-4.薄く均一に重ね塗りを行う
一度に厚く塗ると、乾燥不良や塗膜の剥がれの原因となります。
塗料は薄く均一に塗り、各層が完全に乾燥してから次の層を重ねることが大切であり、一般的には2~3回の重ね塗りが推奨されます。
4-5.乾燥時間の確保
塗装後は最低でも24時間の乾燥時間を設け、完全に乾くまでウッドデッキの使用を控えましょう。
乾燥が不十分だと、塗膜が傷つきやすくなります。
塗料の種類によっては完全に硬化するまでに数日かかる場合もあるため、製品の説明をよく確認し、適切な乾燥時間を確保することが重要です。
4-6.塗装後の仕上がりをチェックする
塗装が完了した後は全体の仕上がりを確認し、塗りムラや塗り残しがないかチェックしましょう。
とくにデッキの継ぎ目や隅の部分は塗料が行き届きにくいため、しっかりと確認が必要です。
仕上がりに問題がある場合は追加で塗装を施し、塗膜の均一性を保ちましょう。
以上のポイントを守ることで、ウッドデッキの塗装を効果的に行い、美しい仕上がりと長持ちする塗膜ができあがります。
5.ウッドデッキ塗装の時期は環境によって異なる
ウッドデッキの塗りなおしの期間は、大体2年前後くらいだと言われています。
しかし立地によって天候条件が異なる上、塗料やデッキの使い方によっても耐用年数に差があるので、あくまで目安としてお考えください。
ウッドデッキは湿気や紫外線に弱いので、気温が高い地域や降雨量・降雪量が多い地域はより短いスパンでの塗りなおしが必要になるかもしれません。
腐食や劣化が進むと、塗料の塗りなおしだけではカバーできないので、普段からデッキの状態を確認しておきましょう。
5-1.劣化状況によって塗装する
ウッドデッキの劣化は、主に以下のサインで確認ができます。
色褪せや塗膜の剥がれ:紫外線や風雨の影響で、塗装面が色褪せたり、塗膜が剥がれてきた場合は、塗装のタイミングです。
苔や藻の繁殖:表面に苔や藻が生えている場合、木材が水分を吸収しやすくなっている証拠です。放置すると腐食の原因となるため、早めの塗装が必要です。
ささくれやひび割れ:木材の表面にささくれやひび割れが見られる場合、劣化が進行しています。安全性の観点からも、速やかな塗装や補修が求められます。
これらの劣化症状が現れたら専門家に相談し、適切な塗装やメンテナンスを検討しましょう。
5-2.定期的な塗装の目安
劣化の進行を防ぐためには、定期的な塗装が効果的です。
一般的な目安として、1〜2年に一度の塗装が推奨されていますが、適切な塗装頻度は設置環境や使用状況によって異なります。
直射日光が強く当たる場所や降雨が多い地域では、木材の劣化が早く進行するため塗装の回数を増やす必要があります。
また、頻繁に人が歩く場所や家具を設置する場合は、摩耗による塗膜の劣化が早まりやすいため定期的な状態チェックと適切なタイミングでの塗装が重要です。
定期的なメンテナンスを行うことで、ウッドデッキの寿命を延ばし美しい状態を長く維持しましょう。
5-3.季節による塗装の適期
一般的に、春や秋の穏やかな気候の時期が塗装に適しているとされています。
気温が15~25℃の範囲で湿度が低い環境のほうが、塗料が適切に乾燥し塗膜の定着も良好になるためです。
また、梅雨や台風の時期を避けることで、塗装面が雨にさらされるリスクを減らし、仕上がりの品質を保つことができます。
一方で、真夏の高温多湿の環境では塗料が過度に乾燥し、塗膜にムラができやすくなります。
さらに冬場の低温時には乾燥不良が起こりやすいため、塗装の効果が十分に発揮されない可能性があるでしょう。
6.人工木のウッドデッキなら塗装の手間いらず
ウッドデッキの塗装やメンテナンスの手間を省きたいなら、耐久性に優れた人工木がおすすめです。
ウッドデッキの塗装は先ほどもご紹介したように複数の工程が必要で、かつ天候にも気を配らないといけないなど手間と時間がかかります。
木材は湿気や紫外線の影響を受けやすく、腐食や劣化がある部分は張り替えもしなければなりません。
人工木は主に金属や人工樹脂などで作られており、天然木よりも劣化しにくく長く使えます。
とはいえ、使用している人工木の素材や品質はメーカーによって異なりますので、人工木ならなんでも良いというわけではありません。
使いやすく、耐久性の高い素材であることが大切ですので、ウッドデッキ設置前にはサンプル材を取り寄せて実際のさわり心地や素材感を確認しましょう。
晴れた日や気温の低い日など、外に数時間置いてみてどれくらい表面温度に変化があるのかもチェックすると実際にウッドデッキを置いた時がイメージしやすいですよ。
7.彩木のウッドデッキ材はこだわりの表面加工で天然木にも遜色ない
彩木のウッドデッキで使われている人工木材「彩木材」は、アルミ芯材をウレタン樹脂で包むことで丈夫さと快適な使い心地を両立しています。
紫外線に強い光安定剤がブレンドされた特殊塗料を用いることで、耐候性実験では20〜30年ほど安定して使い続けられるという結果が出ました。
天然木のウッドデッキは2~3年程度のスパンでメンテナンスや塗りなおしが必要ですが、彩木のウッドデッキは簡単な掃除だけでも美しい状態が長持ちします。
硬質低発泡ウレタン樹脂とアルミ芯材を組み合わせることで、ウレタン樹脂の縮みやすさや金属の熱くなりやすさというデメリットも解消し、季節を問わず使いやすい素材に仕上がりました。
彩木は機能面だけでなく見た目の美しさにもこだわっており、複数の天然木から模様をかたどり、職人による立体的な塗装を施すことで天然木にも負けないナチュラルな風合いに仕上がっています。
まとめ
ウッドデッキの塗料にはステインと像膜型があり、それぞれ木材へのアプローチも違います。
とはいえ程度は違っても、塗りなおしやその都度の下処理が必要な点は同じです。
塗装の度に数日かけて作業しなければならない上に、場合によっては木材の取り換えも必要です。
優れた人工木を使ったウッドデッキなら、手間をかけずに綺麗な状態を長く楽しめます。
記事中でご紹介した彩木を使った専用キットは、ミニサイズから10帖サイズまでの広さが選べ、組み立ても数時間で行えます。
特殊な塗装とコーティングにより、再塗装やメンテナンスも不要。
詳しくはこちらのページからご確認ください。
同じカテゴリの最新記事
ウッドデッキ、バルコニーの製品一覧
ウッドデッキ・ガーデンデッキの施工例
RANKING
人気ランキング